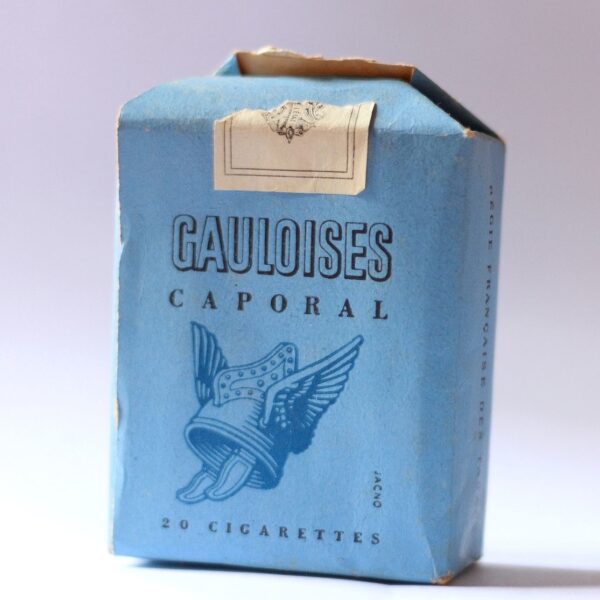「見えること」よりも「ものの見方」が大事とは、セザンヌやマルセル・デュシャンも、それぞれに強調していた極意ではないか。その認識は、遠くギリシアのイデアに、ヴァザーリの素描論やレオナルドのカルトンと響き合う。素描/ドローイングとは、世界を見ようとする意志によって、世界を開くための不断のエクササイズであり、時を超えてつづく遊戯なのだろう。
先のエッセイ集の中で、美術史家のエドガー・ヴィントの言葉を借りて、レヴィ・ストロースも幻滅を漏らしている今日のスペクタルな展覧会の氾濫、写真や映像を濫用したそのコンテンツには、情報資本主義の畜群としてブラインド化された観衆の影が、プラトンの<洞窟の比喩>のように映っている。
ニスや修復の絵の具の層に覆われた美術館の仄暗いタブローの森のなか、変色した紙葉に浮かぶサンギーヌ(代赭色のチョーク)や銀筆の描線、あるいは展示ケースに開かれた画帳に走る墨線の消息に出会うとき、それが描かれた、失われたはずの時に響いていた画家の脈拍を自分の内に聴いて、生気を取りもどすのは、ひとり自分だけの幻覚なのだろうか。
鷹見明彦(美術評論家)